こんにちは〜。
台湾在住のryoです。
普段台湾の企業で働いて日本に向けて仕事をしていると「あ〜また日本休みかあ」と思うことがあります。
台湾は日本と比べると、祝日の数がとても少ないんですよね。
でも、有給の消化率は相当高いです。なぜなら、台湾では消化できないしきれなかった有給はお給与として翌年に振り込まないといけないから。
会社としては、休んでもらわないと余計な支出になるので、休みを推奨してます。
ほかにも、慶弔休暇がきちんと取られていたりと、祝日は少ないものの、台湾の有給(特別休暇・慶弔休暇)はとてもわかり易くて、ホワイトなんです◯
この記事では、台湾で働くひとに、労働者の権利である有給(特別休暇・慶弔休暇)について台湾政府の資料を参考に、日本のお休みと比べながらわかりやすく解説してみます。

使えるもんは全部使おうぜ!
台湾と日本の有給休暇と比べてみました
労働法上には特別休暇・慶弔休暇・病欠と労働者のお休みが決まっています。
このページでは、特別休暇・慶弔休暇・病欠の3種類の休みについて、台湾と日本の比較をしていきます。

台湾政府(中華民国労働部)の情報はネット検索で一発で出てくるし、簡潔で超わかりやすいがすばらしい!
特別休暇
台湾の特別休暇
台湾の労働法上の休暇は、本当にシンプルでわかりやすいんです。
中華民国(台湾)の労働部公式ホームページにアクセスすると、休みの種類と内容、根拠となる労働法がすべてリストになっています。

休みの種類、原則とその根拠を一覧表にまとめてくれるのが一目瞭然で超いい(語彙)
| 休みの種類 | 原則 | 根拠 |
|---|---|---|
| 休日 | 週休2日制(2日休みのうち1日を規定の休み、1日を休息日とする) | 勞動基準法第36條 |
| 祝日 | 內政部の定める国立記念日や祝日のほか、勞動節や中央主管機關の指定した休日。 | 勞動基準法第37條 |
| 特別休暇(有給) 半年未満〜1年 | 3日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 半年~満1年目 | 7日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿2年目 | 10日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿3年目 | 14日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿4年目 | 14日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿5年目 | 15日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿6年目 | 15日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿7年目 | 15日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿8年目: | 15日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿9年目 | 15日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿10年目 | 16日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿11年目 | 17日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿12年目 | 18日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿13年目 | 19日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿14年目 | 20日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿15年目 | 21日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿16年目 | 22日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿17年目 | 23日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿18年目 | 24日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿19年目 | 25日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿20年目 | 26日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿21年目 | 27日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿22年目 | 28日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿23年目 | 29日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 滿24年目 | 30日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |
| 25年以上 | 30日 | 勞動基準法第38條特別休假試算表 |

日本の特別休暇
お次は我が国日本の特別休暇についてです。
これ探すのがめっちゃ大変で。台湾のようにググって一番上に超見やすい政府の資料が出てきたりしないので、数ページ目まで確認するとやっと「厚生労働省」が出している特別休暇に関する資料を発見!
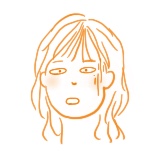
台湾と同じように、なんとか表にまとめてみると、こんな感じ。
| 休みの種類 | 原則 | 根拠 |
|---|---|---|
| 休日 | 労働は、1日に8時間、1週間に40時間まで | 労働時間・休日(厚生労働省) |
| 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩が必要 | 労働時間・休日(厚生労働省) | |
| 少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日が必須 | 労働時間・休日(厚生労働省) | |
| 有給(特別休暇) | (1)6ヶ月間継続勤務し、(2)その6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合は、10日の有給を与える。 | 年次有給休暇取得促進特設サイト |
| 6ヶ月の継続勤務以降は、継続勤務1年ごとに1日づつ、継続勤務3年6ヶ月以降は2日づつを増加した日数(最高20日まで)を与える | 年次有給休暇取得促進特設サイト |
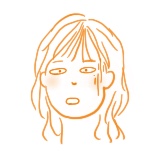
でも辞めるときにやっとまとめてとる人が多いよね。数年前の有給は消滅しちゃってるパターンも…。
慶弔休暇
慶弔休暇(けいちょうきゅうか)とは、自分自身や近親者の慶事(結婚・出産)、近親者の弔事(葬式)の際に取得できる休暇のこと。こちらの休暇についても、台湾と日本を比べてみます。
台湾の慶弔休暇
| 休みの種類 | 原則 | 根拠 |
| 結婚 | 8日間 | 勞工請假規則第2條 |
| 忌引き休暇 |
| 勞工請假規則第3條 |
当時急遽日本へ帰ることになったのですが、有給を使うことなく丸6日休むことができました(休むには、お葬式の通知など正式な書類を人事に提出する必要がありましたが)。これは会社によるかもしれませんが、私の会社では「見舞金」も出ました。
また、結婚すると「結婚休暇」も8日間自動的に付与されます。

結婚休暇の場合も、「結婚証明書」を人事部に提出する必要があります。
日本の慶弔休暇
厚生労働省や法務部が出している資料が見つからなかったので、民間のサイトを参考にすることにしました。
それもそのはず、日本では慶弔休暇は労働法上の「休暇」と定められておらず、企業によって福利厚生のひとつとして出されていたんです。
就業規則や雇用契約書の定め方次第で有給扱いか無給扱いかも変わるようで、結局は会社次第ってことですね。
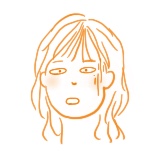
労働法で定めていないのだから、中小企業や零細企業では出さなそうですね。有給すら使い切らないんだし、まずは有給消化でってなるわな
ちなみに、国家公務員の慶弔休暇は以下のように定められています。
| 本人の結婚 | 5日 |
| 妻の出産 | 2日 |
| 忌引き休暇 | (1)父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者の場合は、7日間 (2)兄弟、祖父母、子女、配偶の父母が死亡した場合、5日間。(3)疎遠の親戚が死亡した場合、3日間。 |

そもそも知らない人が多いから「有給つかおう」ってなる気がする

私の母も義父がなくなったとき申し訳なさそうに有給とってたな…
その他、労働法上に規定のある休み
そのほか、台湾の労働省が公開する休暇一覧には病欠や労災負傷、用事があって休む(台湾では「事假」といいます)などがあります。
これらの休みも、労働法上で「何日まで」と決まっていて、その間は完全に「有給」ではありませんが「半給」が支給されたりします。
| 休みの種類 | 原則 | 根拠 |
| 病欠 |
| 勞工請假規則第4條 ※基本は半給です。詳細はリンクで確認できます。 |
| 労災病欠 | 職務中に事故などで治療が必要になった場合、「病欠」とみなす | 勞工請假規則第6條 ※基本は半給です。詳細はリンクで確認できます。 |
| 私用の休み | 1年で14日間を超えないこと | 勞工請假規則第7條 ※無給です。 |
| 公式休み(政府規定の台風休みなど) | 政府の通達により休みになる | 勞工請假規則第8條 ※基本有給です。 |
実際、労働法通りに休みが取れるの?
台湾の場合
取れます。私も祖父が亡くなったとき、6日取りました。
でも何の準備もなく1週間丸々休むのは私の仕事上難しいので、3〜4日くらい丸々休んで、2日くらいはパソコンを持っていき会社と連絡と取れるようにしておきました。
有給は給与として買い取ってもらえるので、病気で休むなら病欠を(半休ひかれるけど、有給は丸1日分の給与がもらえる)、慶弔休暇ならその通り申請するようにしてます。

労働者の権利ですから
日本の場合
消化率100%はかなり厳しいですよね…。正社員である母は、夫である私の父の両親が亡くなったときも土日繋げて1〜2日の休みしか取れず、辞めるときにやっと全部の有給を使ってました。

といっても3年くらいで消失するようで、10年働いた全ての有給は使い切れなかったみたいです。
まとめ
台湾の会社はそもそも「給与が低い」という最大の欠点があるのですが、「休みを取りやすい」というところでは日本よりは働きやすいのかな、と思っています。
マネージャーでも年に2回くらい大型連休を外して2週間程度の長期海外旅行に家族といけちゃうので、自分が生活できるくらいの給与でいいから決められた時間だけ仕事して給与もらって、楽に働きたいっていう人には、東南アジアで数年働いてみるのもありですね。
それでは、また~。
台北情報ブログと、海外就職ブログのランキングに参加しています。
よろしければクリックお願いします ( ˊᵕˋ )


コメント